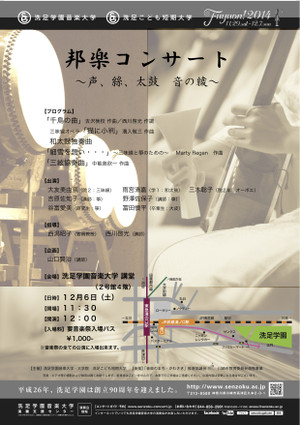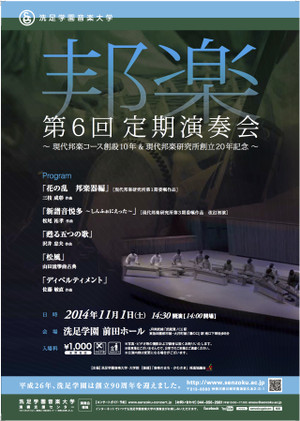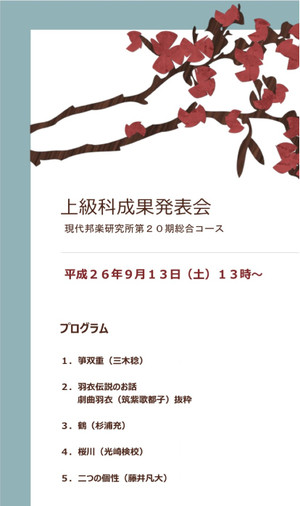第20期修了コンサート
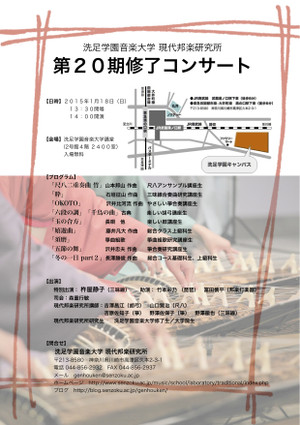
下記からチラシをダウンロードできます。
【日時】2015年1月18日(日) 13:30開場 14:00開演
【会場】洗足学園音楽大学講堂 (2号館4階 2400室) 入場無料
【プログラム】
「尺八二重奏曲 竹」山本邦山 作曲 尺八アンサンブル講座生
「粋」 石垣征山 作曲 三味線合奏曲研究講座生
「OKOTO」沢井比河流 作曲 やさしい箏合奏講座生
「六段の調」「千鳥の曲」古典 楽しい胡弓講座生
「玉の合方」長唄 他 楽しい鼓講座生
「嬉遊曲」 藤井凡大 作曲 総合クラス上級科生
「須磨」箏曲組歌 箏曲組歌研究講座生
「五節の舞」沢井忠夫 作曲 箏合奏研究講座生
「冬の一日 part2」長澤勝俊 作曲 総合コース基礎科生、上級科生
【出演】
特別出演: 杵屋静子(三味線)
助演: 竹本彩乃 (琵琶) 冨田慎平(邦楽打楽器)
司会:森重行敏
現代邦楽研究所講師:吉澤昌江(胡弓) 山口賢治(尺八)
吉原佐知子(箏) 野澤佐保子(箏) 野澤徹也(三味線)
現代邦楽研究所研究生 洗足学園音楽大学修了生/大学院生
【問合せ】洗足学園音楽大学 現代邦楽研究所
genhouken@senzoku.ac.jpまで